近年、パワハラをはじめとする様々なハラスメントに対する意識が強まってきました。
仕事のミスは確かに自分も改めなければいけないところですが、過度な注意や個人攻撃、口うるさく攻めてきたり、仕事ができないまでに干渉してくるのは、立派なパワハラです。
しかし、簡単に仕事は辞められない…というのが実情ではないでしょうか。
家族がいたり、介護する両親がいたり、人によって事情は様々です。
ですが、パワハラがなくならない限り、現状は全く変わりません。
今回は、職場におけるパワハラやいじめに関する対策法をまとめてみました。
「口うるさい上司のせいで仕事ができない」はパワハラ?

実際の職場で、毎日仕事をしてく中では、やはりミスがつきもの。
そしてミスには注意や指導が必ず入るでしょう。
しかし、その注意や指導が、本当に「適切」なのか。
そこが一つ、パワハラかどうかの分かれ道になります。
「上司に叱られるけど、私にだけ当たりがきつい気がする」
「仕事できないくらいに、長時間叱ってくる」
「同じ一つのミスを何回もネチネチ言われて、正直うるさいと思ってしまう」
実際にパワハラを受けている人の精神的苦痛は、想像を絶するものです。
パワハラや職場の人間関係で精神疾患になってしまう人は年々増えており、とうとう、2020年に「パワハラ労災」というものが施行されました。
それだけ、目に見えないところでパワハラに苦しんでいる人が多い、ということです。
うつ病や適応障害などの精神疾患になってしまうと、自分自身も苦しいですし、休職中のお金の心配も出てきます。
精神的に辛い、と思ったら、一刻も早い精神科や心療内科の受診が必要です。
パワハラ被害者は、多くが一つの疑問にぶつかるとされています。
それは、「自分が受けている叱責(あるいは行為)は、本当にパワハラなのか?」という疑問です。
特に精神的に痛めつけられている場合、正しい判断ができなくなっているので、「これはパワハラじゃないかもしれない」「みんな我慢している」など、パワハラであるということを受け入れないケースが多いです。
では、実際、どこまでがパワハラとして認められるのでしょうか?
厚生労働省は、パワハラの定義について、平成30年に文書を出して以下のように整理をしました。
検討会報告書においては、以下の①~③の要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントの概念と整理。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること。
- 業務の適正な範囲を超えて行われること。
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
引用:厚生労働省より
つまり、まとめると、パワハラの定義は
「職場内での優位性や立場を利用し、労働者に対して、業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせを行うこと」
となります。
つまり、
- 業務時間外に電話やSNSでうるさく叱責などの連絡してくる
- 業務時間内でも、業務ができないほど長時間叱責する
- 殴る、蹴るなどの身体への暴行や、嫌がらせをしてくる
などは、パワハラとして当てはまることになる可能性があります。
現代は暴行に関してはすぐに対処されるため、目に見えないところでの嫌がらせや、言動によるパワハラも多いのが特徴です。
精神的にしんどくなってしまったら、一刻も早く、自分の身を守りましょう。
会社は、助けてはくれません。
あなたの精神的な健康は、家族のためにもなるのです。
口うるさい上司で仕事ができない環境をどうすればいいのか
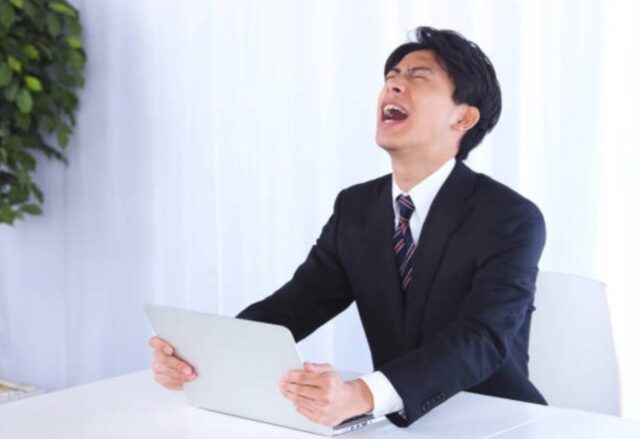
最近は、いろいろなハラスメントがあります。
パワハラは上司から部下へ、会社での立場の優位性を利用して業務外で不適切な叱責や嫌がらせをしたり、業務内でも逸脱した叱責行為や嫌がらせを行うものでした。
ですが、部下から上司への逆ハラ、パワハラとも近い関係のセクハラやモラハラ、マタハラなど、たくさんのハラスメントがあります。
職場の環境が整っていなければ、当然仕事はできないし、職場の雰囲気を悪くするでしょう。
仕事中もずっとうるさいおしゃべりを続けている同僚や、自分は何もせずうるさいことだけ言ってくる上司など、仕事ができない環境はいくらでも考えられます。
そして、もしあなたが職場環境について、上司に進言したら…。
それがパワハラへとつながるかもしれない、という恐怖もありますよね。
精神疾患は、真面目な人がなりやすい傾向がある、と様々な統計で明らかになっています。
真面目な人こそ、上司への進言をしたり、うるさい環境でも我慢して自分は仕事をしたり…という傾向があるのでしょう。
真面目に仕事をしていて、パワハラにあってしまうなどということもあり得るのです。
しかし、なかなか職場の環境を変えるというのは難しいのが現実でしょう。
うるさい人はいつでもうるさいでしょうし、PCのタイピング音がうるさい、という人もいますが、タイピングをするな、というのも無理があります。
仕事ができないほどに上司からの叱責があったとしても、上司を変えることはできません。
つまり、環境を変えることはほぼ無理です。
では、どうすればいいのでしょうか?
①休職する
とりあえず一旦、精神を休める、という方法です。
医師の診断書があれば、会社は休職願いを受領せざるを得ません。
しかし、復帰したときにまた同じ職場に戻るということになるので、根本的な解決とはなりにくいのが現実です。
また、休職中の給料などの保証がある会社とない会社がありますので、お金の面でも心配があります。
実際、休職からの復帰の際、再び精神疾患を再発させてしまうというケースが多いのが現状です。
休職中の転職活動については下記の記事で詳しく解説しています。
②異動願いを出す
これは上司や職場の環境を変えられるチャンスです。
しかし、次の部署でうまくいくとは限りません。
新しい仕事も覚えないといけないという点や、何より同じ会社なので、元の部署の人と関係を断ち切れない、という点からも、なかなか踏み切れない方が多いのではないでしょうか。
③転職する
これは、今までの職場の人間関係をリセットすることができるパターンです。
しかし、実際に仕事をしながら転職活動をするのは難しい、という印象があるのではないでしょうか。
転職には年齢も関係しますし、ハードルは高いように思えます。
ですが、今までの会社にいて、本当にこれから残りの人生を、その会社に勤めながら生きていけるのか?と考えたとき、どう思いますか?
求職や移動のいずれかを選択した方も、結果復帰して精神疾患を再発させ、退職となった、というケースも多く見られるのです。
再発したうつ病や適応障害は、最初の症状よりも重く、また治りにくいケースが多いと言われています。
下記の記事では年代別に転職成功のポイントを解説しています。
転職を考えている方はぜひご覧ください。
口うるさい上司から身を守ることを第一に考える

職場でのいじめやパワハラなどのハラスメントは、精神的に大きな負担になります。
仕事という「逃げにくい環境」で追い詰められていく中で、徐々に正常な判断ができなくなっていきます。
パワハラされている状態に「慣れ」てしまうのです。
そうなる前に、早めの医療機関への受診が勧められます。
うつ病や適応障害には、単に気分の落ち込みや感情の起伏の他に、「身体症状」と呼ばれるものがあります。
精神の問題が、体に出てしまうのです。
それは人によって様々で、めまい、頭痛、腹痛、下痢、睡眠障害など、放っておけないものが多数あります。
ストレスで胃が痛い、というのは、こういった精神的な問題が体に現れた、「身体症状」の代表なのです。
自分の体の調子も合わせて、ストレスに対して自分の体がどう反応しているか、軽く見ずに医療機関を受診してください。
口うるさい上司からパワハラにあったらどうするの?
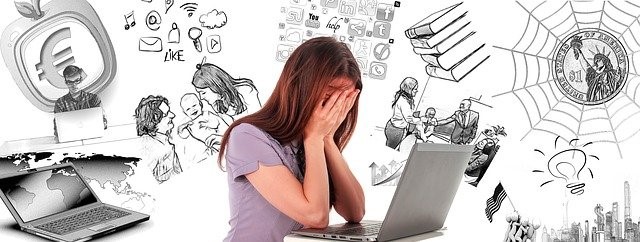
平成28年に、パワハラを受けたと認識した後、自分はどのような行動をしたか、調査が行われました。
その結果、「何もしなかった」という回答が40.9%と最も多くなったのです。
参照:平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書
近年は暴力行為に対する世間の目も厳しくなっています。
当然、パワハラをする方は世間から責められたくないですから、目に見えるような、あるいは痕に残るようなパワハラはなかなかしないでしょう。
つまり、それは、後々に第三者が「これはパワハラかどうか」「どの程度のパワハラだったのか」を判断する時に、問題が出てくるということです。
パワハラの記録を残すこと
とにかく必要なのは、記録に残すことです。
記録に残らないだろうから、とあなたを好き勝手にしている上司は考えているかもしれません。
スマホの録画、録音や、I Cレコーダーなどの記録が望ましいですが、無理であればメモを残しましょう。
これは、後々パワハラ労災などの認定を受ける際、有力な証拠となります。
いつ、どんなことをされたのか、をしっかり記録してください。
会社の相談窓口(社内機関)に相談する
本来相談相手となるべき上司のことは、会社の相談窓口や、人事部に相談しましょう。
部署に相談できる相手がいない状況ならば、部署の外に相談するしかありません。
ただ、「会社に上司のことを告げ口したみたいで怖い」「もっと上司から嫌がらせされるかもしれない」と心配になることもあるかと思います。
しかし、会社などの組織は、こういった相談者が相談内容で不利益にならないように、プライバシーの確保や配慮をすることが求められています。
問題なのが上司だけでなく、部署全体がうるさい、雰囲気が良くない、仕事ができない環境であることも、上司に言えない場合は会社の相談窓口や人事部に相談しましょう。
外部の相談窓口に相談する
会社というのは組織です。組織である以上、「自分の組織に不利益な存在は隠す」といった隠蔽体質がないとも言い切れません。
勇気を出して内部の相談窓口や人事部に行ったのに、むしろ居心地が悪くなった、という方や、最初から会社組織を信用していない方は、こちらの方法がいいでしょう。
外部の相談窓口というと、総合労働相談コーナーなど、全国の労働局や労働基準監査署に設置されている24時間無料の相談が可能な窓口が挙げられます。電話でも相談できるので、夜遅くまで残業があっても、相談ができます。
パワハラの相談した後はどうすればいいの?

相談して、解決するのならば良いのですが、多くの場合は解決には至らないようです。
しかし、パワハラがあった事実を認めてもらうという意味でも、内部・外部の相談窓口は効果的です。
とにかく精神的な攻撃から逃れ、身を守ることを最優先にしてください。
病院を受診し、自分の状態を第三者に確認してもらうことも大切です。
医師からの診断書があれば、会社側は休職の許可を出すしかありません。
しかし、休職してから、あるいは異動してから退職するにせよ、通らなければいけないのが、退職の手続きです。
この退職の手続きが、一つ大きな壁になっています。
「またあの上司の顔を見なければならない」
「仕事できないくせに生意気、なんて言われそう」
「うるさいだけで仕事ができないなんて、本当に受け入れられるのか」
不安は尽きないと思いますし、そもそももうその職場に行きたくもないはずです。
現在、そんな方のために、「退職代行サービス」というものがあるのはご存知でしょうか?
「退職代行ガーディアン」は、「もう会社と関わりたくない」「もう二度と行きたくない」「職場の人間と話したくない」といった希望者に代わり、退職手続きを全て行ってくれるサービスです。
こちらの「退職代行ガーディアン」は、
・料金は業界でも安価の29,800円即
・即日即時対応ですぐに退職が可能
・会社とのやり取りは一切不要
・退職届や貸与品・私物のやりとりも郵送でOK
・退職できない場合は全額返金
・もうパワハラ加害者と話す必要なし!
とパワハラを受けた人の強い味方となってくれます。
下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
まとめ
今、自分が受けている行為はパワハラなのか。
仕事ができないほど追いつめられるような環境や、うるさくて仕事ができないような環境は、どうやっても耐えられるものではありません。
我慢すればするほど、逆に加害者はエスカレートすることもあるのです。
必ず周囲に助けを求め、利用できるサービスを利用し、自分の心をしっかりと守ってください。
何よりも大切なのは、会社でも仕事でもありません。
あなた自身なのです。







